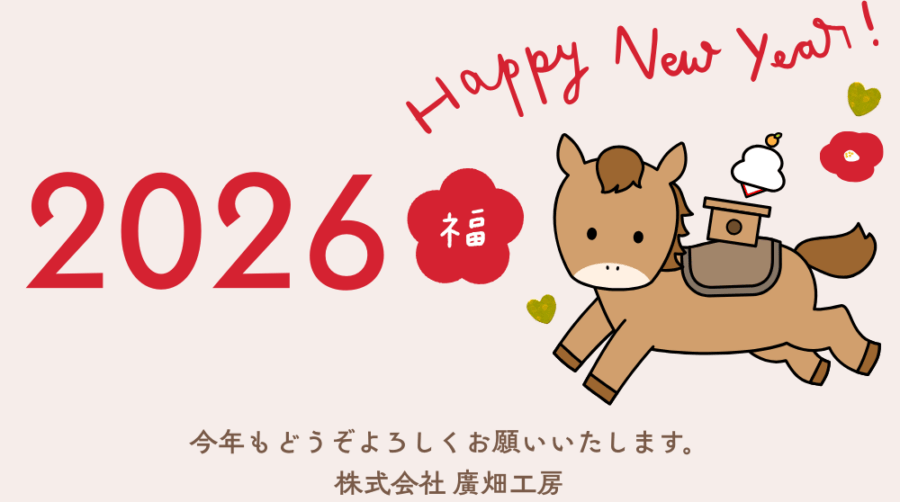
新年のご挨拶―お客様の満足する家づくりを続けていくこと
廣畑工房について
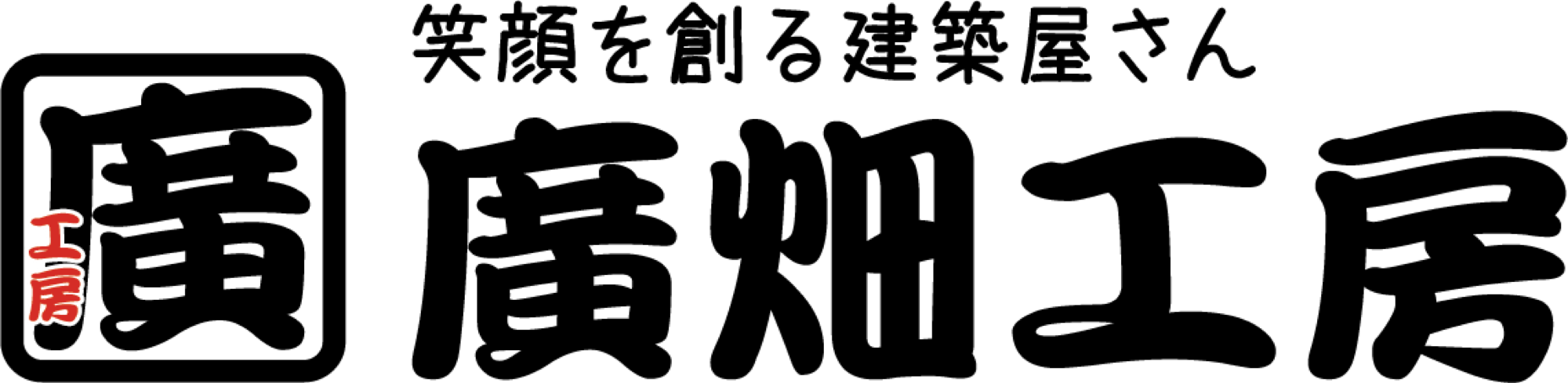
家づくりコラム
こんにちは!御前崎市で大工が作るマイホームを手掛けている廣畑工房です。
日本の木材自給率は約40%で、そのうち建築用で使用されるのは50%ほど。つまり、国内で使用される全木材の80%は輸入材なのです。
各ハウスメーカーや工務店がどのように木材を選び、家づくりを行っているのか、それぞれに特徴があります。
今回は、廣畑工房のつくる家の木材についてお話しします。

■国産材と輸入材
国産材やその地域の県産材を使用するメリットは、風土に合った家づくりができること。
特有の気候の中で育った木でつくられた家は、環境に馴染みやすく、長持ちするという考え方です。また、輸送費が抑えられ環境面にも良いという点もあげられます。
費用面を抑えるなら、輸入材の方が向いています。国産材の自給率が低いことからも分かりますが、国産材は確保できる数が安定しないため、確実なルートを持たなければ、お客様の家づくりが不安定になっています。 輸入材の強みは、強度などの品質が国産材より優れている樹種があること。昨今の未曾有の災害を思えば、大きな地震にも耐えられる頑丈さを求める声も多くなりました。

■劣化を最小限に抑えるための適材適所
廣畑工房の家づくりで重要にしていることは、やはり「住み続けられる家」「長持ちする家」であること。
木造住宅の平均寿命は30年ほどです。当然ですが、建てたばかりの新築の状態が30年続くわけはなく、経年劣化していきます。いつかは建て替えやリフォームをしなければならないとしても、それぞれに劣化が少ない素材を選んで使用することで、その平均寿命を延すことができます。 当社では、国産材、地域材、輸入材をそれぞれの木材の性質・特徴に合わせ、適する部分に使用した、適材適所の家づくりを行っています。

■国産材と輸入材の使い分け
大手メーカーではSPF材を使用するところがあります。北米の針葉樹であるスプルース・パイン・ファーの頭文字をとってSPF材と呼ばれ、ホームセンターなどでも安価に購入できます。これらの木材は、短期間で大きく成長するため木目が詰まらず、柔らかく湿気に弱い性質を持ちます。海に面した御前崎市のような地域には不向きかもしれません。
当社の適材適所とは具体的に、構造材には県産材、外部木下地や外壁材の中の胴縁には国産ヒノキ、柱や土台には国産材、梁や桁には輸入ベイマツというような使い分けをしています。 例えば、土台には抗菌・防虫作用があり、耐久性が高いという理由でヒノキやヒバを採用しています。柱にはある程度の強度ながら加工しやすく、流通しているという理由でヒノキやスギを用いています。屋根周りには国産材の合板を使用します。伸び縮みが少なく、高温多湿の日本の気候に適するからです。

部分に合わせ適する木材を用いることで、劣化が少なく長寿妙な家をつくることができます。あらゆるものにおいて国産品は好まれやすいですが、お客様の暮らしを守るためにも、廣畑工房は産地問わず、素材の特徴を生かし、長持ちするお家づくりを心がけています。